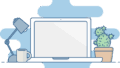―JA流通と政府備蓄がつくる“鉄壁フロア”
5行まとめ(ここだけ読めば要点OK)
- JAグループが国内コメの過半を集荷し、出荷量を調整して価格を下支え
- 全農(JA全農)が卸への販売価格を事実上の指標にしており、小売はその“天井”を超えにくい
- 政府は毎年約21万tを買い入れ、備蓄100万t前後を常備して“下値”をガード
- コメ先物市場は取引量が小さく、市場ベースの価格形成が機能しづらい
- 結果、小売用袋米は為替や国際相場が下がっても数%しか動かない構造が続く
1. JA集荷システム――“入口”で量を握る
| 指標 | 数値・ポイント |
|---|---|
| 集荷シェア | 全国平均 54%(北海道80%・九州75%) JAcom |
| 全農の役割 | ①集荷米を一括保管 ②精米業者・卸に販売 → 取扱量が多い都道府県では**“全農値”が地域の基準相場** |
| 価格調整 | 例年9月の作柄・需要見通しを基に ◎ 生産者保管量の呼びかけ ◎ 集荷価格の微調整 で出荷ペースをコントロール |
ポイント
JAは「農家の販売窓口」「保管倉庫」「金融」の三位一体。集荷量を握ることで需給を人為的に平準化でき、米価の急落を回避しやすい。
2. 政府備蓄米――“出口”で価格を支える
| 項目 | 仕組み | 数値 |
|---|---|---|
| 適正備蓄水準 | 大不作に備え、約100万tを常備 | 2024年6月末:91万t残高 農林水産省農林水産省 |
| 買入ペース | 毎年播種前に20〜21万tを契約買入 | |
| 放出ルール | 原則売却せず5年保管→飼料用や輸出用に回す | |
| 価格効果 | 不作年でも“国家買い入れ”で瞬時に需給タイト化→ 下落リスクを排除 |
イメージ
- “価格が崩れそう”=政府が買い増して在庫を積み上げ
- “豊作で余り米”でも棚上げ保管→ 市場に出てこない=価格は維持
3. 卸・小売マージン構造と値付け慣行
| 流通段階 | 典型マージン | 備考 |
|---|---|---|
| 精米業者 → 卸 | 2〜3円/kg | 精米歩留・保管リスク込み |
| 卸 → 小売 | 5〜8円/kg | 買い切りが多く過剰在庫リスク小 |
| 小売 → 消費者 | 10〜15円/kg | “特売”でも2〜3円/kg値引きが限度 |
- 袋売り(家庭用)市場は年1%縮小 ─ “量より単価”で利益を確保
- 新米期(10〜11月)を除き、年間での店頭価格変動は±5%程度
- 為替や国際相場が下がっても、国内産中心ゆえ転嫁しにくい
4. 米先物市場が育たない3つの理由
- 取引高が少なく価格指標になりにくい(出荷の54%をJAが握り先物を使わない)
- 消費者や外食が「国産ブランド」を重視=輸入米ヘッジの需要が薄い
- “現物渡し”が産地限定で配送コスト・品質差が大きい
2021年、大阪取引所のコメ先物は参加者不足で本上場を断念—市場メカニズムが働く窓が閉じたまま。
5. まとめ & 次回予告
要点3行
- JAと全農が集荷量・販売価格の基準を握り、下振れを抑制
- 政府備蓄が100万tの“防波堤”となり、市場へ余剰が流れない
- 卸・小売も薄利固定で、消費者価格は小幅にしか動かない
次回は**「輸入規制と需要減少なのに高値が続く真の構造」**を解説します。