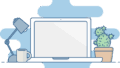―生産サイドから読み解く“高コスト構造”と減反政策
5行まとめ(これだけで要点OK)
- 60kgあたり生産費は平均約2万円で、米国の約3〜4倍 ─ 小規模・高齢経営が多い
- 減反(げんたん)政策が半世紀続き、需給を人為的にタイト化
- 生産費を補填する交付金で「値崩れ」リスクを政府が肩代わり
- 規模拡大や機械共同化が遅れ、コスト低減スピードが鈍い
- 結果、原価が高止まり→流通でも下げ余地が乏しく米価は底堅い
1. 減反の歴史と“面積調整”のメカニズム
- 1970年開始:「米余り」を防ぐため作付面積を国が割り当て
- 2018年“廃止”後も、自治体ごとに生産数量目標→実質的には継続
- 作付制限で需給が締まり、市場に米がダブつかない=価格維持
- 2024年でも転作交付金(10aあたり3.5万円前後)が“インセンティブ”に 農林水産省
キモ:自由栽培に戻っても“暗黙の減反”が残るため、生産量は伸びず価格は緩みにくい。
2. 1俵(60kg)=平均 2万5千円超 のコスト構造
| 主なコスト項目 | 背景 |
|---|---|
| 家族労働費 32% | 農家平均年齢68歳。家族労働依存が高く、効率化しにくい |
| 資本利子・地代 22% | 自作地でも機会費用算入。狭小田で機械当たり収量が低い |
| 物財費 18% | 肥料・農薬・資材が円安で高騰(2024年は前年比+18%) |
| 機械費 15% | 田植機・コンバイン等“専用機”を個人保有=減価償却が重い |
| その他 13% | 乾燥調製・水利費など |
農水省統計(令和4年産)では作付0.5ha未満層は60kg=2.58万円と、50ha超の約2.5倍 農林水産省農林水産省
3. 補助金・交付金が“米価フロア”を支える
| 制度 | 仕組み | 直近額(目安) |
|---|---|---|
| 水田活用直接支払交付金 | 麦・大豆など転作に10aあたり3.5万 | 1,400億円/年 |
| ナラシ対策 | 価格急落時の収入補填 | 500億円規模 |
| 畑地化・機械導入補助 | 50%補助など | 年度ごと |
- 価格が下がると交付金で赤字を穴埋め=農家は値下げ圧力を感じにくい
- 税負担でセーフティネットを敷くため、市場メカニズムが働きづらい
4. 高齢・小規模経営が多数:効率化の壁
- 農家の約7割が作付1ha未満(2023年)
- 平均年齢は68.4歳で、リスクを取った投資が難しい
- 共同利用組合やスマート農機リースは拡大中も、
広域・大規模経営へ集約は欧米比で進行遅れ 農林水産省
5. まとめ & 次回予告
要点3行
- 高コスト+補助金で“損しない構造”→価格が下がりづらい
- 減反の名残で需給がタイト=余剰在庫が出にくい
- 規模拡大が遅れ、国際価格との差は依然3〜4倍
次回は 「JA流通と政府備蓄がつくる “価格ガード” の仕組み」 を掘り下げます。